フルートのタンポ交換してみました。
2016-10-31こんにちは!そしてハッピーハロウィン!( ノ ・ω・)ノ( ノ ・ω・)ノ( ノ ・ω・)ノ☆
大変ご無沙汰しております、名古屋栄店のきたむらです。
今日は楽しい楽しいハロウィ?ンですが、皆さま楽しんでますか?
さてさて、調整中の楽器がいくつかあるので
その中からフルートの『タンポ交換』の様子をさくっとご紹介。
今日はヤマハのYFL-211SIIのタンポを交換してみます。
ちなみにこれ ↓ は、オーバーホールするために分解した、フルートの管体です。
キィがついてないので、なんか変な感じですよね( ・ω・)

交換前のタンポの状態
交換前のタンポはこんな感じです。

タンポがトーンホールを塞ぐときにつく、丸い跡のことを
『轍(わだち)』というのですが、これはそこそこ黒ずんでますね?( ・ω・)
(ひどい状態だと、虫食いになっているタンポもいらっしゃいます)
タンポをカップから取り外す
タンポは『ワッシャー』と『ビス』という2つのパーツで
カップに収まっているので、それを外します。

ドーナツ状の板がワッシャー、その横のネジがビスです。
10円玉と比べるとこんなサイズ感です( ・ω・)
調整台紙と調整紙
ワッシャーとビスを外すと、タンポも外れます。
タンポを外すと、またまたドーナツ状のパーツが出てきました( ・ω・)ノ◎

これは『調整台紙』と呼ばれる紙で、同じメーカーでも
大きさや厚さといった様々な種類があります。
たとえばヤマハの場合、0.2mm、0.1mm、0.08mm、0.05m
といった厚さがよく使われています。
下の画像でいうと、上の列が調整台紙です。
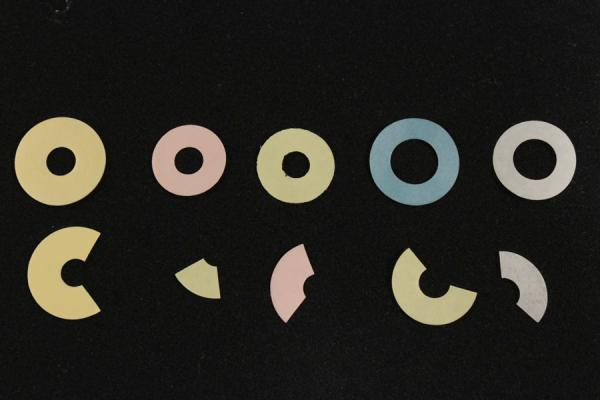
下の列の紙切れみたいなものは『調整紙』と呼ばれ、
調整台紙を細かくカットしたもののことをいいます。
この調整紙は、厚さ、カットする大きさ、カップのどこに置くかによって
タンポの塞がり具合がかな?り変わってくるので
結構重要なポイントだったりします( ・ω・)
一般的には、カップ→調整台紙→調整紙→タンポ→ワッシャー→ビス
といった順番に重なっていきます。
新しいタンポを取り付ける

はい、取り付けました。
左が交換前、右が新しいタンポなんですが一目瞭然ですね!
新しいタンポはつるんとしていますね?( ・ω・)
交換したタンポを調整する
これを管体に組んで、トーンホールをきちんと塞げているか
確認するのが、この『フィラー』というアイテム!

といっても爪楊枝にクリーニングペーパーをくっつけただけですが
これがないと、ひじょ???に困るので、調整の際は必須アイテムです( ・ω・)
今回はクリーニングペーパーですが、わたしはカセットテープを使うときもあります。
このフィラーでチェックをしながら、トーンホールが
塞がっていないところに、先ほどの調整紙を入れたり、
調整台紙を変えたりしながら、タンポを調整していきます。
フルートのタンポはかなりデリケートなので
例えば今日タンポ交換して、トーンホールを塞げても、次の日には隙間ができてる!
なんてこともよくあります。。
なので、時間をかけて合わせていくので
フルートの調整は少し時間がかかってしまいます( ´ ・ω・)
こんな感じでタンポの調整が終わったら
全体のバランスを調整して、フルートの調整が完了です!
タンポ交換については、破れていたり、虫食いタンポは交換するのはもちろんですが
タンポがどういう状態になったら交換するのか、という判断は
状況や、技術者によっても変わってくるので、自分のタンポは交換時期かな?と
思ったらお近くのリペアマンに相談してみてくださいね?( ・ω・)ノ☆
担当:きたむら