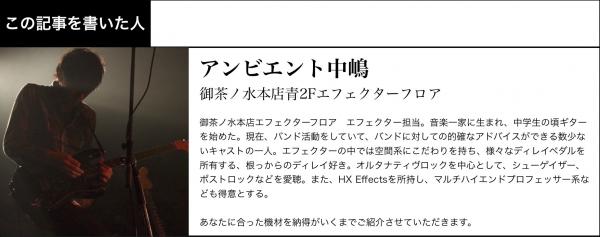ベーシストに愛され続けるエフェクター
2019-07-23 皆さんこんにちは。イシバシ楽器御茶ノ水本店エフェクターフロアの
アンビエント中嶋です。
HELIXファミリーに搭載されています。
各エフェクトのモデルを一つ一つ掘り下げていこうと思います。
今回ご紹介するのはDistorsionモデルからZeroAmp BassDIです。
ZeroAmp BassDIは【TECH21 / SansAmp BASS DRIVER DI】をベースとしております。

こちらのモデルはベーシスト御用達、超定番プリアンプDI、Tech 21 SansAmp Bass Driver DIですね‼︎
いわゆるベーシストに大人気、サンズです。
ベース用のプリアンプと言ったらこいつ。
どんなベーシストでも一度は導入を検討したことがあるのではないでしょうか。
モデリングする元がVersion.1というところも熱いですね。
知らない方も多いのではないでしょうか、実はサンズにはバージョンが存在するのです。
そんなSansAmp Bass Driver DIの解説、いきましょう!
ベーシストの超定番プリアンプ
よくベーシストの間で「サンズ」と呼ばれていますが実は正式名称はSansAmp Bass Driver DIとなっており、SansAmpはあくまでもTech21の中のSansAmpシリーズとなります。どちらかといえばベードラの方が正しくはあるのですが正直BassDriverと名のつくエフェクターは数多くあるのでどちらもややこしい呼び名になっております。
SansAmpシリーズとして、1989年に発売された「SANSAMP CLASSIC」は、世界で初めてチューブ・アンプ・エミュレーション回路の開発に成功をしました。
それまではチューブ・アンプのサウンドはマイクで撮るしかなく、ラインレコーディングはできませんでした。
SansAmp Classicはどちらかというとギター用のエフェクターになるのですが
それ以降ベースで使用する人が増え、それからベース用が発売されて大ヒットしたそうです。
そんなプリアンプですが、その後様々な進化を遂げて今もなお現行品として販売されております。
バージョンの違い
サンズといえば、僕が真っ先に思い浮かぶのがNUMBER GIRLの中尾憲太郎さんのサウンド。ピック弾きしたくなる、鉄板を叩いたようなトレブル感が気持ちいいサウンドですね。
「鉄風 鋭くなって」のリフを今でも弾いてしまいます。
そんなサンズでも数々の種類のものがあります。
V1はボリューム、ゲイン、ブレンド、そしてトレブル、ベース、プレゼンスのEQが付いております。
サンズといえばこいつを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
そしてBass Driver DI-LB、白文字が印象に残る日本限定の仕様が印象深いですね。
こちらはベースのドロップチューニングや多弦ベースの超低域を出せるようになったモデルです。
そしてV2、最大との特徴はミドルのつまみが搭載されたこと。
そしてスイッチによりベースとミドルの帯域を変更できます。
簡単に言ってしまえば、今までの機能全部入りです。
他にもParaDriverDIなど紹介していない機種もございます。
どのモデルもサンズの音はしてくれるのですが、サウンドのニュアンスが全く違います。
さてHELIX側のパラメーターの説明に行きましょう
パラメーターの解説
・Drive
歪み量の調整が出来ます。時計回りにまわしていくと歪み量が増えていきます。
・Bass
低音の調整が出来ます。
・Treble
高音の調整が出来ます。
・Presenc
超高域の調整が出来ます。
・Blend
原音と歪みの調整が出来ます。
・Level
音量の調整が出来ます。
歪み量の調整が出来ます。時計回りにまわしていくと歪み量が増えていきます。
・Bass
低音の調整が出来ます。
・Treble
高音の調整が出来ます。
・Presenc
超高域の調整が出来ます。
・Blend
原音と歪みの調整が出来ます。
・Level
音量の調整が出来ます。
とこんな形になっております。
オススメの使い方は、というよりもベーシスト全般におススメです。
こいつで歪みを作れば、バンド内のアンサンブルに迷うことは無くなるでしょう。
それほど考えられてるサウンドが出ます。
スナップショットを生かし、歪みが強いサウンドやハイの痛くないギリギリをついたサウンドなど、DSPを節約しつつ、曲に必要な最適なサウンドで鳴らしましょう。
中音のバランス、今までのシステムとの相性を考えた際に、やはりアンプシュミレーターではなくエフェクトモデルでサウンドを作るのはとても作りやすいかと思います。
エフェクターの種類をたくさんは使わない方はHX Effects、HX Stompでの導入を検討されてみればいかがでしょう。
それぞれおけるブロック数が9個、6個となっていますのが、
ボードをコンパクトにまとめられるのは、今のバンドマンのニーズに合ったものになっていると思います。
今回はここら辺で!
また次回お会いしましょう!!

他にもこんなモデルも紹介しています