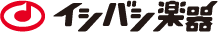文:白井英一郎(池袋店・アコースティックフロア)
昨年秋に14作目のアルバム『スタンディング・イン・ザ・ブリーチ』をリリースしたジャクソン・ブラウンが、新しくヴァッル・マッカラム、グレッグ・リーズ(元ファンキー・キングス)を加えたバックアップ・バンドを従えて、この3月に7年ぶりの単独来日公演を果たす。
ジャクソンはアメリカのウエスト・コーストの音楽シーンを代表するシンガー・ソングライターの一人だ。ニッティ・グリティ・ダート・バンド(以下NGDB)の元メンバーであり、イーグルスのデビュー・ヒット、「テイク・イット・イージー」の共作者としても知られる。現在66歳のジャクソンは、1972年のアルバム・デビュー以降現在に至るまで継続的に活動をおこなっている。彼がデビューした当時のウエスト・コーストの音楽シーンはカントリー・ロックの創成期を迎えていた。シンガー・ソングライター達も少なからずその影響を受け、アーシーなアコースティック・サウンドとロック・サウンドを融合させていた。ジャクソンもその例に漏れなかったが、変わらぬ風貌とともに今も青臭さを残し当時のスタイルを貫いている。また自他共に認めるプレイボーイであるジャクソンだがレパートリーにラブ・ソングは少なく、身の回りの出来事を題材にした内省的なナンバーが多い。また社会的なメッセージ色を濃く打ち出した時期もあった。彼の歌声にはカリフォルニアをイメージさせる奔放さと陰りが同居し、また繊細な感性が見え隠れする。シンプルなバンド・サウンドに乗せて、時には軽快に、時には憂いや哀愁を漂わせ、また時には優しく、時には力強く訴えかけ、リスナーの心を掴んできたのである。
プロフィールや作品リストについてはオフィシャル・サイトを参照いただくとして、ここでは一ファンかつ楽器愛好家の目線でジャクソンを紹介していこう。
70年代のロサンゼルス・ミュージック・シーンの象徴的存在
気取りのないジャクソンのパフォーマンスは、友人ブルース・スプリングスティーンのようなカリスマ性を感じさせるものではない。しかしながら、聴衆のリクエストや呼びかけに気さくに応じる姿勢には友人のような親近感を覚える。会場にコンサート終了を告げる案内放送が流れ、客席の照明が灯されたにもかかわらず、鳴り止まぬアンコールに応えて演奏を再開することも珍しくない。神経質な側面も持つが、サービス精神も旺盛である。
またジャクソンをデビューさせるために、かのデイヴィッド・ゲフィンがアサイラム・レコードを設立したことは語り草だ。そのアサイラムの同胞イーグルス、リンダ・ロンシュタット、ジョン・デイヴィッド・サウザーらが刺激や協力をしあって、ロサンゼルスのミュージック・シーン自体を商業的成功に結びつけていった。それは創造的でロマンチックな70年代のウエスト・コースト・ロック黄金期を象徴する出来事だった。彼らがたむろしたサンセット通りの名門クラブのトルバドールや、ロサンゼルス近郊のローレル・キャニオンやトパンガ・キャニオンで育まれたミュージシャンのコミュニティは、熱心なファンの間では神話となっている。
1976年、雑誌『ポパイ』が創刊され日本にウエスト・コースト・ブームが巻き起こり、当地のファッション、ライフ・スタイルが日本に紹介された。当時青春時代を過ごしたファンにとっては、音楽のみならず、ウエスト・コーストのミュージシャンの交遊、ライフ・スタイルもまた興味や憧れの対象となった。またジャクソンは環境活動家の側面もあるが、それも自然回帰の潮流の中でファンに好意的に受け入れられた。この頃イーグルスは「ホテル・カリフォルニア」で60年代のカウンター・カルチャーやカリフォルニアン・ドリームの終焉を告げていたが、イーグルス、リンダ、ジャクソンらの立ち振る舞いが新たなロマンを抱かせたのである。

ジャクソン・ブラウン・ファースト Original recording remastered
ジャクソンの似顔が描かれたファースト・アルバムのジャケットは、今なお70年代を感じさせるサーフ・ショップやアメリカン・スタイルのミュージック・バーの壁に飾られている。かつての友人イーグルスは桁違いの成功を収めスターの仲間入りをしてしまったが、ジャクソン・ブラウンは今なお70年代のままの、フレンドリーなLAのローカル・ミュージシャンの雰囲気を残している。そんな彼の姿に、古くからのファンは郷愁と安心感を覚え、若いファンは良き70年代へ憧れの念を抱き、そしてタイム・スリップしていくのである。
代表的な作品
ジャクソンの歴代作品を振り返ると、大きな音楽性や曲調の変化がないのが分かる。しかしながら評価が高いのは、70年代から80年代前半にかけて発表された比較的初期の作品群だ。収録されたナンバーは佳作揃いで、上述のような時代的背景が相まって根強い人気を誇る。
もし、これからジャクソンを聴くのであれば、最初の一枚としてまず傑作の誉れ高い『レイト・フォー・ザ・スカイ』(74年)を推薦したい。タイトル・トラックを筆頭に「悲しみの泉」、「ダンサーに」、「ビフォー・ザ・デリュージ」など淡々と歌いかけるナンバーが多いが、ぐいぐいとリスナーを引き込む力強さを秘めている。盟友デイヴィッド・リンドレーがギター、ラップ・スティール、バイオリンで縦横無尽に活躍。特にタイトル・トラックでの歌心溢れるギター・ソロは心を打つ。ジャケットの写真も印象的で、三作目にして大変完成度の高い作品に仕上がっている。

孤独なランナー Original recording remastered
また、ライブ盤『孤独なランナー』(77年)もお勧めしたい。収録されたナンバーは全て新曲で、ステージでの演奏はもちろん、ツアーの合間にツアー・バスやホテルの部屋で収録されたプライベートな演奏も含まれているのが面白い。上述のデイヴィッドに加え、セクションのメンバーやローズマリー・バトラーによる息の合ったサポートが素晴らしい。躍動感溢れるタイトル・トラックは今でもコンサートのハイライト曲となっている。ローズマリーのパワフルなコーラスと、デイヴィッドのドライブの効いたラップ・スティールがこのナンバーを盛り上げている。またラストを飾る「ザ・ロード・アウト」と「ステイ」のメドレーもコンサートの定番ナンバーだ。前者はジャクソンを支えるローディへのトリビュート・ソング。後者はモーリス・ウィリアムスのヒット・ソングのカバーだが、歌詞が変えてあり、オーディエンスに会場に残って欲しいと呼びかけている。仲間やファンを大切にするジャクソンの気持ちが伝わってくる。
リリース年は前後するが、『フォー・エブリマン』(73年)も押さえておきたいアルバムだ。前述の「テイク・イット・イージー」やNGDB、グレッグ・オールマンがカバーした「青春の日々」が収録されている。前者はスニーキー・ピートが奏でる宙を舞うようなペダル・スティールを前面にフィーチャーし、ビートを利かせたイーグルスのバージョンよりもレイドバックしたアレンジで聴かせてくれる。バラード・ナンバーの後者は、青臭さが残るジャクソンのボーカルにデイヴィッド・リンドレーのラップ・スティールが印象的に絡む。他にもロックンロール・ナンバーの「レッドネック・フレンド」などコンサートでお馴染みの楽曲が多い。
盟友デイヴィッド・リンドレー
近年は弾き語りや上述のデイヴィッド・リンドレーとのデュオ活動をおこなうこともあるが、基本的な演奏スタイルはレコーディング、ライブともにバンド形式だ。バック・バンドはギタリスト(1~2名)、キーボーディスト、ベーシスト、ドラマーで構成されることが多く、ジャクソン自身もアコースティック・ギター、エレクトリック・ギター、ピアノを演奏する。パーカッショニストやコーラスのためのシンガーを従えることもある。歴代のサポート・メンバーはロサンゼルスの凄腕プレイヤーが名を連ねる。また、デイヴィッド、ローズマリー・バトラーのように、ジャクソンのサポートをきっかけにして広く知られるようになったプレイヤーもいる。
中でも、デイヴィッド・リンドレーはジャクソン・ブラウンを語る上で最重要プレイヤーと言える。デイヴィッドはジャクソンの古くからの友人で、かつてはサイケデリック・バンドのカレイド・スコープに在籍していた。ギター、ラップ・スティール、フィドル、各種民族楽器等様々な楽器を器用にこなす職人肌のマルチ・プレイヤーである。ジャクソンのアルバムへの参加は『フォー・エブリマン』が最初だが、以来ジャクソンとデイヴィッドの息のあった演奏が一つの売り物となっていた。特に注目されたのはスライド・プレイだ。一般的なギターではなく古いリッケンバッカー、ナショナルなどのラップ・スティールを使い、エモーショナルかつ巧みなバーさばきで他のギタリストとは一線を画した独自の境地を築いている。ハワイアンの楽器、ラップ・スティールをロックの世界に紹介した功績は大きい。また前述の通り、「レイト・フォー・ザ・スカイ」のエレクトリック・ギター・ソロも名演の一つに数えられており、ジャクソンの作品への貢献度は高い。80年代に入りデイヴィッドはソロ活動のため一旦ジャクソンの下を離れるが、その後も交流は続いた。そして、近年再び共演するようになっている。
ジャクソン・ブラウンの使用ギター

Gibson CF-100E
※参考画像
ギター・コレクターでもある彼は多数のギターを所有しており、ステージにずらりと並んだギターを目撃したファンも多いだろう。それでは主な楽器を紹介しよう。
まずはアコースティック・ギターから。近年比較的良く使用している物としては、1930年代製Gibson Roy Smeck Stage Deluxe、1994年製Gibson Roy Smeck Stage Deluxe Reissue、1950年代製Gibson CF-100、1950年代製Gibson CF-100E、1940年代製Gibson LG-2、1950年代製Martin OO-17、1970年代製Martin D-41 Sunburst、1960年代前半製と思しきMartin D-28、1966年製Epiphone Troubadour、Roy McAlister 14-fret David Crosby、Roy McAlister Roy Smeck typeなどが挙げられよう。これらは幾つかの異なるチューニングにセットアップされているそうだ。
なお、Roy Smeckのシリーズは12フレット・ジョイントの大柄のボディを持つモデルで、元々ハワイアン・ギター(膝の上に寝かせて弾くギター)で、非常に幅広なネックが採用されている。近年発売されたジャクソンのシグネチャー・モデルの基になったギターでもある。ジャクソンはこのモデルを相当気に入っており、Roy McAlisterにも同タイプのギターを作らせたくらいだ。CF-100Eはソロ・アコースティック・ライブの際には、Fender Bandmasterアンプに繋ぎトレモロを掛けて「孤独なランナー」で使用していたのが印象的だった。また、そのRoy McAlisterはジャクソンの友人でもあるデイヴィッド・クロスビーがお気に入りのルシアーだ。かつてはSanta Cruzでギター製作をおこなっていた。当時から彼の手掛けたギターはミュージシャンの間で高い評価を得ていたようだ。

Martin D-41
※参考画像
上記のほかにも、GibsonのJ-45やSouthern Jumbo、Gurian、Takamineなど様々なアコースティック・ギターを使用してきている。なかでもジャクソンが70年代中ごろに使用していたGurianはほとんど無名だったが、彼のおかげで存在が知られるようになったと言える。また世界にその名を轟かせた日本を代表するエレアコ・ブランドTakamineは、70年代末から80年代初頭にかけて、ジャクソン、デイヴィッド・リンドレー、ライ・クーダー、イーグルスなどウエスト・コースト・ロック系アーティストがこぞって使用して注目をされた。ウエスト・コースト・ファンにはTakamineも馴染み深いブランドの一つだろう。なお、ピックアップ、プリアンプのシステムは、ニール・ヤングの影響でTrance Audioのピックアップ・システムを好んでいる。
次にエレクトリック・ギターだが、残念ながらアコースティックと比較するとジャクソンのエレクトリック・ギターについて詳しく言及された資料は少ない。しかしながら、エレクトリックもまたビザール・アイテムを含め様々なモデルを使用してきている。今回のツアーのプロモーション写真では、ジャクソンはブロンドのGibson ES-345を持っている。また最近の映像にはMartin F-55らしきギターの姿もある。セミアコがマイ・ブームなのだろうか。過去の公演ではStratocasterやTelecasterタイプのギターの使用が多かった。1979年の反原発コンサートの模様を収録した『ノー・ニュークス』のビデオでは、テレキャスタータイプのネックが付いたサンバーストでべっ甲柄のピックガードがついたストラトキャスタータイプのギターを使用していたのが印象的だった。
3月のコンサートでは、どんな楽器が飛び出すのか、今から大変楽しみである。
文:白井英一郎(池袋店・アコースティックフロア)
イシバシ楽器でギターを探す

Gibson LG-2
※参考画像

Martin D-41
※参考画像

Martin D-28
※参考画像

Gibson J-45
※参考画像

Gibson Soutern Jumbo
※参考画像

Takamineギター
※参考画像
Amazonで購入
関連リンク
白井英一郎プロフィール

間もなく勤続33年目に突入するベテラン。ルーツ系からコンテンポラリーな物まで様々なジャンルの音楽を聴くが、特にウエスト・コースト・ロックへの造詣が深い。音楽ライターとして、レコード・コレクターズ、プレイヤー、DIG、CROSSBEATなど専門誌への執筆が多数ある。演奏活動もおこなっているが、横浜の有名ライブ・ミュージック・レストラン、Thumbsup恒例のライブ・イベントWest Coast Session "Something Fine”のレギュラー出演者でもある。