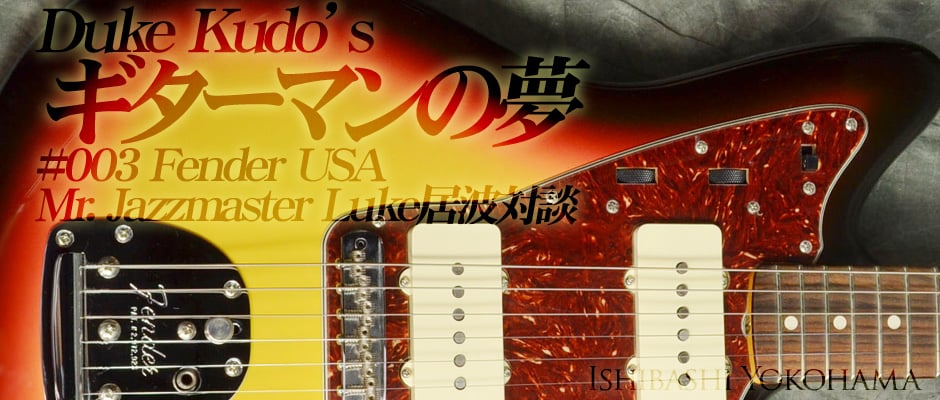現在でも根強い人気を持つジャズマスターは、1958年に米フェンダー社よりジャズミュージシャンをターゲットに発表されました。 当時のジャズギタリストの間ではギブソン社のレスポールの使用が一般的であり、フェンダーのギターはジャズには不向きであるという傾向にありました。そこに一石を投じるべくフェンダー社の創業者レオ・フェンダーはジャズに対応できるギターの開発に着手しました。
そのような背景の中生まれたジャズマスターは、当時のラインナップの最高機種であり、フェンダー社としては初めてローズウッド・フィンガーボードを採用、また座って演奏することの多いジャズミュージシャンを意識した左右非対称のオフセット・ウエイトと言われるボディーデザイン、従来のシングルコイルより太く甘いワイルドコイルピックアップ、フロントピックアップ用プリセット回路、滑らかなアーミングが可能なフローティング・トレモロなど多くの新しいアイデアが採用されました。1966年からはブロックインレイ、ネックバインディングが施されるようになり、その後何度かマイナーチェンジを繰り返しながら1980年頃まで生産されました。生産中止後も需要が途絶えず、1999年より再生産販売が開始されました。
ジャズマスターの力強く芯のあるサウンドは、1960年代のサーフミュージックに大きな影響を与えました。1990年以降はオルタナティブロック系のギタリストに愛用され、近年ではシューゲイザー系ギタリストにも多用されるなど幅広く使用されています。


DUKE工藤

プリセット回路

トレムロック横から

弦落ちした状態

ムスタング・ブリッジ
DUKE:今回はイシバシ楽器のミスター・ジャズマスターこと、LUKE居波をゲストに迎えジャズマスターの魅力に夢を見たいと思います。
ジャズマスターの魅力とは?
LUKE:ジャズマスターの最大の魅力はやはりそのコシのある太く甘いサウンドにあります。リアポジションで歪ませ、パワフルにジャキジャキ鳴らすのもかっこいいですが個人的にはセンターポジションを軽く歪ませた芯の通ったクランチサウンドが最高です。またフロントポジションでの太いサウンドも魅力的でメロディーを弾かずとも単音を伸ばすだけでとても良い雰囲気を醸し出します。
DUKE:ミックス・センターポジションはレオ・フェンダーもお気に入りのポジションでフロントとリアのマグネットを逆磁にコイルの巻き方向を逆巻きにしたハムキャンセル効果にして配線は並列にしたミックス・サウンドが出せるように設計しました。(直列配線にすればいわばハムバッキング・ピックアップとして機能します)ギブソンのように直列にしたハムバッキングサウンドより高域の残るシングルトーンに魅力を感じていたのでしょうね。
LUKE:ジャズマスターにはフロントピックアップ用のプリセット回路が付いており、スイッチを上に上げると回路が切り替わります。このプリセット回路は通常のフロントポジションのサウンドよりも更に甘いサウンドに設定されており、トーン、ヴォリュームのプリセットが可能です。主にバッキングとソロの使い分けとして使うのが一般的ですが、プリセット回路側のヴォリュームをゼロにし、キル・スイッチとして使ってみるのも面白いと思います。
最近ではこのプリセット回路をキャンセルしているプレイヤーも多く、ソニックユース、サーストン・ムーア・シグネイチャーのジャズマスターなどは、最初からプリセット回路がとりはずされています。
DUKE:プリセット機能は当時フェンダー社副社長のフォレスト・ホワイトが、レオ・フェンダーに出会う前の1930年代には考案し1944年には自作のスティール・ギターに組み込んだそうです。
考案のヒントは、ライブ中のミュージシャンがリズムとリードパートの音量を変えるのに一生懸命ボリュームをいじりながらコントロールしていたのを見て、プリセットがあれば楽なのに、と思って考案したそうです。このアイデアは1958年にプリセット機能がついたソリッド・ボディ・エレキギター・ジャズマスターに繋がりました。
またマーク・ケンドリックを見出したのはフォレスト・ホワイトといわれています。リジェンドは繋がりますね。
DUKE:フローティングトレモロについて特徴を教えてください。
LUKE:従来のシンクロナイズドトレモロのような深いアーミングはできませんが、滑らかなヴィブラートを掛けることが可能です。アームの先端を手で握り、そのままストロークすると音が微かに揺れ、幻想的なサウンドを生み出すことができます。特にマイ・ブラッディ・ヴァレンタインのケヴィン・シールズなど、シューゲイザーのジャンルではメジャーな奏法であり、ジャズマスターをお持ちの方は是非一度試して頂きたいです。
また、ジャズマスターのフローティングトレモロにはトレムロックという機構がついており、弦が切れたりした場合でもチューニングを崩さない効果があります。チョーキング等の際の不必要なトレモロの動きを制御することもできるので、アームを使わないという方にもオススメです。
DUKE:ジャズマスターを使っている方で弦落ちに悩まされている方も多いのではないでしょうか、特に、力強くコードをかき鳴らすジャンルなどでは大変大きな問題だと思います。ライブ中に弦が落ちてしまったら。想像するだけで不安ですが何か改良方法はありますか?
LUKE:ジャズマスターにもともと使われているのはネジ型のスパイラルサドルですが、構造上ブリッジに掛かるテンションが弱く強く引くと弦が落ちてしまいがちです。
最もポピュラーな改善方法はムスタングブリッジに変え、バズストップテンションバーを取りつける方法です。ムスタング・ブリッジに替えると弦落ちは防げますが、やや金属的でソリッドなサウンドに変化します。またバズストップ・テンションバーを取り付けてのアーミングにも変化が現れます。
そこでジャズマスターの甘く太い音を継承しつつ、滑らかなアーミングが欲しい! という方におすすめなのはMastery Bridge です。僕も使用していますがこれはステンレス製のブリッジで、ボディに完全にフィットし、弦を変えた時にも、演奏中にも動いたりすることはなく、弦の振動をそのままボディへ伝え、サスティーンも伸びるようになります。取り付けの際の加工も不要であり簡単にセットできるのも魅力的です。このブリッジにはM1、M2の二種類があり、M1がUSA規格、M2がJAPAN規格です。(あくまで個人的な意見です)
ジャズマスターは一見扱いづらい印象のあるギターですが、使ってみると抜け出せない素晴らしいギターです。 これを期に是非、ジャズマスターを使ってみてはいかがでしょうか。
DUKE:ありがとうございます。
それでは今回はMastery Bridgeを使用したプレイを動画でカモン!!
Performed by 林勇希

LUKE居波

プリセット回路のないモデル

トレムロック機構

ヴィンテージ・スパイラルサドル

マステリー・ブリッジ

LUKE居波・プロフィール
プロフェッサー岸本の愛弟子であるデューク工藤に師事し横浜店にてギターを担当。
デューク工藤に見出され、ギブソン・ファクトリーにも訪問して選定買付け等を行っており、彼自身のフェイバリットミュージックはオルタナ、ポストロック、シューゲイザーなど現代的なものから70~90年代のロックまで幅広く愛聴している。
常にお客様の立場に立ち、最高の1本を探すお手伝いをさせて頂きます。
横浜店にご来店の際はお気軽にお声掛けくださいませ!
ギターマンの夢・バックナンバー

#010 フェンダーカスタムショップ トッド・クラウス特集

#009 2015ギブソンUSA最新スペック特集

動画特別編:#008 フェンダートーンの魅力を追いかける

#007 Fender 60th Anniversary 1954 Stratocaster #006 ギターマン、アメリカ・フェンダー工場に行く part3 #005 ギターマン、アメリカ・フェンダー工場に行く part2 #004 ギターマン、アメリカ・フェンダー工場に行く part1 #003 Mr. Jazzmaster Luke居波対談 #002 Gibson / Custom Shop BYRDLAND FLORE Vintage Sunburst #001 GIBSON MEMPHIS CUSTOM 1959 ES-335TD HISTORIC BURST
デューク工藤・プロフィール
 渋谷店での6年間に数々のリジェンダリーを経験。その後池袋店にてスターキー☆星と出会いリジェンドを伝承する。ただいま横浜店で新たなるギターマンの夢を追いかけている。
渋谷店での6年間に数々のリジェンダリーを経験。その後池袋店にてスターキー☆星と出会いリジェンドを伝承する。ただいま横浜店で新たなるギターマンの夢を追いかけている。
彼自身のフェイバリットミュージックはロック、カントリー、ブルースとサウンド面でもギターサウンドに精通。
「宝物探しのお手伝いを親切丁寧にいたしますので心より御来店お待ちしております。」(Duke)
林勇希・プロフィール
 音楽学校メーザーハウスにてギターを養父貴氏、宮坂直樹氏、音楽理論を藤原泰樹氏に師事。ロック、ポップス、R&B、ファンク等幅広いジャンルにて活躍中。卒業後は様々なアーティストのレコーディング、ライブサポート活動を行う他、自身のバンド、Sweety Cokeで都内を中心に精力的に活動中。 R&B、Popsを中心とした歌ものバッキングには定評がある。
音楽学校メーザーハウスにてギターを養父貴氏、宮坂直樹氏、音楽理論を藤原泰樹氏に師事。ロック、ポップス、R&B、ファンク等幅広いジャンルにて活躍中。卒業後は様々なアーティストのレコーディング、ライブサポート活動を行う他、自身のバンド、Sweety Cokeで都内を中心に精力的に活動中。 R&B、Popsを中心とした歌ものバッキングには定評がある。
※商品、スタッフの所属等は2014年当時の情報です。予めご了承ください。
Copyright © 2014-2026 Ishibashi Music Corporation. All Rights reserved.