ネック ・ フィンガーボード(指板)
ポジションマーク ・ フレット

ネックとは…↓
|
ネック部分は振動系の全体を支え、音程決定という演奏上最も重要な部分である。 ネック本体には主にメイプル、マホガニーが使われているが、 強度だけを考えるとメイプルが良いと言われている。 ネックの断面形状はギター操作性の点で一番問題となる部分である。 断面形状は現在のギブソンのタイプと、ギブソンのオールド・タイプ、 そしてフェンダー系の3タイプ。 この形状については指板のR、広さ、ネックの厚さと微妙な関係があり、 さらには個人的な好みや奏法の違いなどから、どのタイプがベストとは言い切れない。 またネックはボディに近づくに従い徐々に太くなり、ヒール部分でボディにジョイントする。 このヒールの形状はハイポジションの操作性を左右してる。 |
ネジで止められている
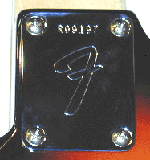
| ネックはボディに直接接着されている”セットネック・タイプ”と、 ビス止めされてボディに取り付けられている”デタッチャブル・タイプ”とがあります。 セットネックはGibson系に多く、LPやSGなどが代表例です。 デタッチャブルはFender系に多くStratocasterやTelecasterに代表されます。 |

フィンガーボード(指板)とは…↓
|
フィンガーボードにはフレットが打ち込まれ、このフレットとブリッジ間の
弦長変化により音程が決定される。弦を押さえた場合、一方の支持端となるフレットを
固定させるためや、チョーキング等の操作、フレット間隔の狂いなどを考慮すると
フィンガーボードはある程度堅く、質量もなければならない。 このため材料にはローズウッド、エボニー、メイプル等が使用される。 フィンガーボード、ネックの反りは非調和倍音であるビリ付きの大きな原因である。 フィンガーボードが逆反りしている状態ではロー・ポジションを押さえた場合、 ビリ付きが生じてしまう。 ビリ付きに対してはむしろ多少順反り気味の方が良い。(もちろん反っていないのがベスト) フィンガーボードは弦の振幅も決定しているため、 ナットやブリッジが高い場合は問題ないが低い場合、 基本波、低次高調波の振幅が制限され、振幅の大きい波形が得られない。 またビリ付きはノイズ的非調和倍音を長振動にのせるが、 ベース奏法には意識的にこのノイズ的非調和倍音を利用したのものある。 |

| Gibson Les Paulの指板。LPはマホガニー材のネックにローズ材の指板を用いたものが 一般的である。ローズ材の以外にもより硬質なマホガニー材を用いたものもある。 ネック部のマホガニー材は、メイプル材と比べると柔らかい材で、Gibson系のサウンドの 大事な要素となっている。反面、ネックとヘッドに角度を持たせているため、 ヘッドに激しいショックを受けた場合には折れ易いというデメリットもある。 |
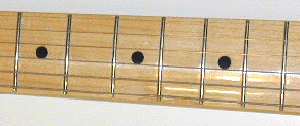
| Fender Stratocasterの指板。ネック材であるメイプルと 指板材を分けずに、一本のメイプル材で成形してあり、また指が触れるその表面部分には 塗装が施してあるのが特徴である。メイプル材は硬質であり、振動の伝達上、 低域周波数がどうしても伝わりにくくなる。したがってFender系のギターは Lowカットされたクリアーで透明感のあるサウンドが特徴である。 |
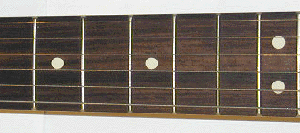
| Fender Stratocasterの指板。指板にはローズ材が用いられている。 |

| Rickenbackerの指板。 |
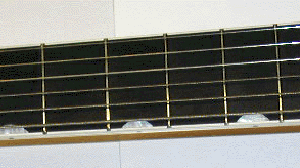
| Gretschの指板。ギターの指板材にはローズ(紫檀)が使われることが多いが、 画像の様に黒みがかった色の材は、より硬質で高級材とされるエボニー(黒檀)の場合が多い。 |

ポジションマークとは…↓
| 指板上の指のポジショニングを視覚的にとらえ、演奏の助けをするものである。 通常は貝やプラスチックが材料として使われている。 その形状は一般的にはドット(●)や四角形が多いが、三角形や星形などもあり、 なかには装飾的な模様を施されたものもある。 多くのギターはポジションマークがあるのが一般的であるが、クラシックギターなどには、 ポジションマークの無いものもある。 |
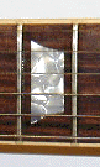
| Gibson Les Paulの台形型ポジションマーク。LPはこの他に機種・年代によって ドットタイプや四角いものもある。 |

| Fender系のドット・タイプのポジションマーク。 指板がメイプルの場合は黒のドットになる。 |
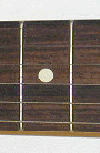
| 同じくFender系のドット・タイプ・ポジションマーク。 ローズ指板の場合は白のドットになる。 |
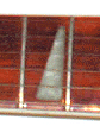
| Rickenbackerのポジションマーク。 6弦側の一点が直角になった三角形のポジションマークが特徴的。 |
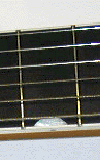
| 指板の中央ではなく、6弦側にしかマークが無いものもある。 画像はGretschのギター。 |

フレットとは…↓
|
弦をこれに押さえつけて希望の音程を出す。ナット側から1フレット,2フレット…と呼ぶ。
フレットは弦を押さえた時、ブリッジとともに支持端となり、
またチョーキング、ビブラート、ハンマリング・オン、ブリング・オフなどの
操作性を左右する重要な部分でもある。 フレットの材料には洋銀や真鍮等が使われ、フィンガー・ボードの溝に打ち込まれる。 フレットの材質による影響は弦振動にも現われるが、 ネック本体、フィンガー・ボードの質量に比べフレット1本当たりの 質量がごくわずかなため、あまり大きな影響は現われない。 フレット形状は様々であるが高さはある程度高い方が良い。 上面の形状によっては弦振動の高域にビリつきを生じさせる。 また表面上の傷はチョーキング等、フレット左右方向のスムーズさを失う原因になる。 |
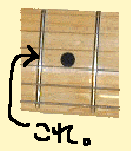
|
