ギターの音程とフレット
|
ところで実際の電気ギターはどのような音をだすのであろうか。
まずギターの弦は→右の図のような基本周波数を開放弦に選んである。
即ち1弦がE4、2弦−B3、3弦−G3、4弦−D3、5弦−A2、6弦−E2であり、
それぞれの周波数は329.628、2460942、195.998、146.832、110.0、82.407Hzである。
また電気ベースでは、1弦−G2、2弦−D2、3弦−A1、4弦−E1であり、
周波数はそれぞれ97.999、73.416、55.0、41.203Hzで、それらの関係を下の図↓に示す。 ギターは今まで述べてきたような規則ある音を半音ずつ発生するために、 フレットで分けられている。 一般にはピックアップを設定するためにフレットの数は限られるが、普通22前後である。 フレットは半音づつ上昇するように設定されているので、 たとえば12フレットになると各弦の周波数はそれぞれ1オクターブ上になり2倍になる。 ギターの出せる音は6弦の開放弦から、1弦の最も高いフレットまでである。 当然の事であるがフレットが多ければそれだけ高い音を出せる。 たとえば、22ふれっとまであるギターだとすると、82.407Hzから1174.659Hzである。 |
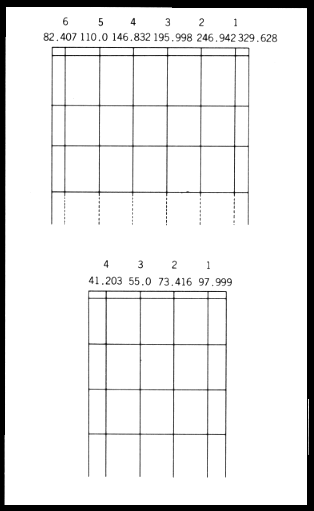
|
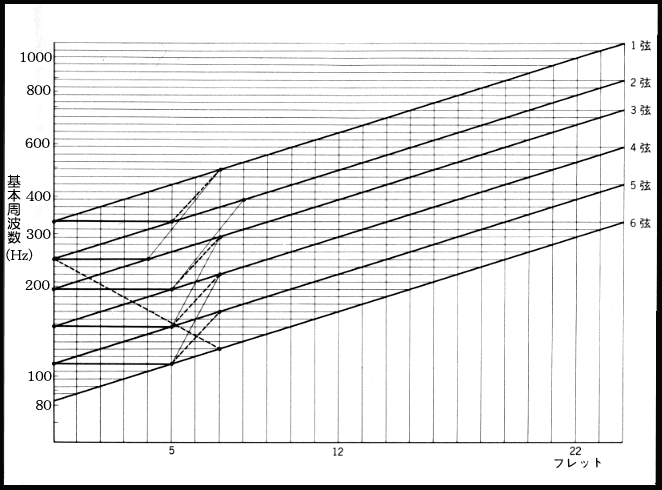
|
| しかしこれはあくまでそれぞれの基本周波数であって、 実際には弦振動のところで述べたように多くの高調波が存在している。 フレットの位置を決定する物理的な根拠は、 弦振動のところで述べた弦の基本振動周波数の式による。 |
|
|
| σは綿密度、Tは張力、Lは弦の長さであり、弦が重い程弦振動周波数は低い。 弦数が大きくなる程弦は太くなり、4、5、6弦、または3弦においても 質量を大きくするために巻弦が使用される。 ギター弦はチューニング・マシンによりその張力を、 しいては振動周波数も変える事ができるが、 今任意の弦の開放弦における希望の振動周波数に張力が合わされたとすると、 右上の式から左の式に書き直され、各フレットの周波数に対して 各フレットの位置を決定することができる。 |
| しかし、左上の式は弦の両端が完全に固定された理想的な値である。 はられた弦と指板は、フレットが存在し接触をさけるために平行であってはならない。 この事は単なる水平距離で弦の長さとそれに対応するフレットが、 決定されるものではないという事である。 各フレットの最もわかりやすい方法を次に説明する。 |
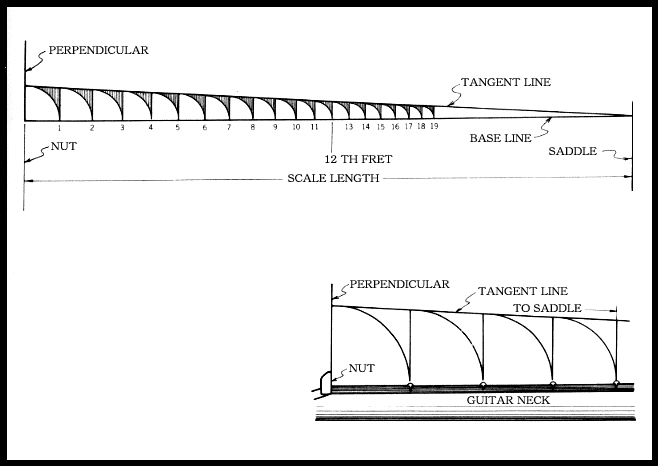
|
|
↑上の図はフレットの説明方法として書かれたもので、ベースラインとして指板を基本にとり、
弦長と周波数の関係に応じて傾きをもった線が引かれている。
この図によればフレットの設計は極端に簡単である。
まずナットの位置からベースラインに対し、垂直線と、
傾斜線との交点との長さを半径として1/4の円弧を描くと、
それとベースラインとの交点が1フレットの位置となる。
1フレットを中心にして同様に行えば、2フレットが
決定され順次各フレットの位置が決定してゆく。 以上は全く幾何学的な方法であるが、簡単な計算で各フレットの寸法を決定する事ができる。 まずスケールの長さが決定するならば、その長さを17.817で割ると、 ナットと1フレットの間隔が決定する。 さらに残ったスケールの長さを同様に17.817で割ると、 1フレットと2フレットの間隔が決定する。各フレットについても全く同様である。 以上に代表的なスケールとフレットのブリッジからの距離、フレットの間隔を示す。 1つは代表的な電気ギター、もう1つは電気ベースのものである。 |
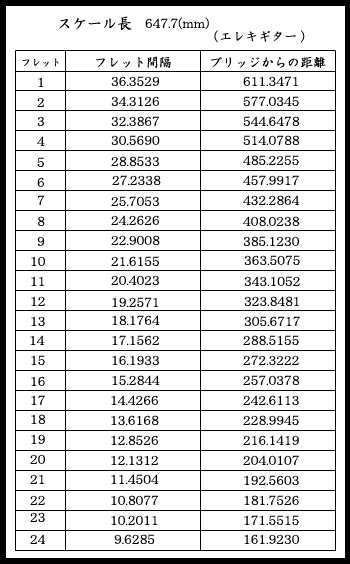
|
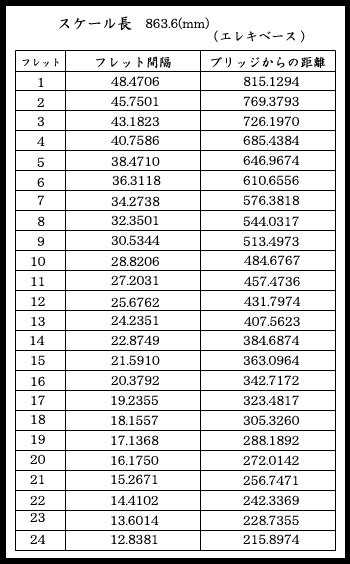
|