
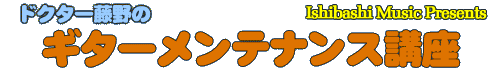
|
弦高について
|
●弦高について ギターの弦高については、専門誌や手引き書などでも説明されていますが、ここで は一般論プラス・アルファをお届けしましょう。 弦高は文字どおり弦の高さのことです。弦の高さは演奏性や音に関わってきます。 通常弦高は12フレットで計ります。一般的に12フレット上で、1弦側は1.8mm〜 2.0mm、6弦側は2.0mm〜2.5mm程度と言われることが多いと思います。しかしな がら、計測するポイントまで紹介されていない例もあるようです。上述の数字は、弦 の下部(指板側)とフレットの頂上部の間のものとお考えください。またネックが反り やねじれなどがないことが前提です。逆に言えば、正常時の弦高を把握しておけば、 湿度、温度の変化を受けてネックに異常が起こったことも発見しやすくなるというこ とです。ちなみにネックの反りのチェックのやり方としては、弦を1フレットと最終 フレットを、それぞれ左手と右手でそっと押えてみるという手があります。押さえた 弦の中央部に0.1mm程度の隙間があれば正常でしょう。それ以上開いていれば 順反り、また弦がフレットに接触してしまうようであれば逆反りの可能性が考えられ ます。ただしこの方法の場合、フレット表面の凹凸や浮きや、ネックのねじれが発生 していると、正しい判断に至りません。もうひとつ、ヘッドの上側からネックの弦を 張ってある側を見下ろす方法があります。ネックの側面がほぼまっすぐに見えれば正 常で、左右一様に弧を描いているようであれば反りの発生が、左右の状況が異なって いるようであればねじれの発生が考えられます。反りやねじれの発生が考えられる場 合は、早めに専門家に相談しましょう。 弦高の話しに戻しましょう。上述の数字はあくまでも一般論です。楽器や、自分の演 奏スタイルにあわせて、多少のアレンジが必要かもしれません。例えば、弦を強くピ ッキングする方は、そうでない方と比べた場合、同じ弦高ではビビリが発生しやすい 可能性があります。自分では他人とピッキングの強さを比較しづらいかもしれません が、例えば使用するピックの厚みが目安となる場合もあります。厚手のピックを好ま れる方は、弦を強くアタックする傾向があると言えます。そういう方は、目安の数字 より高めに設定した方が、ビビリを回避するという意味では理想的でしょう。またス トラトキャスターとムスタングの2本をお持ちだったとします。ご存知の方も多いと 思いますが、ストラトキャスターはスケール(=弦長: ブリッジからナットまでの距 離)が長く、ムスタングはそれが短いのですが、同じ弦を張った場合、前者より後者 はテンションが少なくなります。テンションが少ない方が、同じようにピッキングし た場合、ビビリやすくなります。もしビビリを軽減したい場合は、短いスケールのギ ターには太目の弦を張るか、弦高を上げるという作業が必要になります。もちろん、 ビビリに神経質になり過ぎるのも禁物です。いずれにしても、数字が先行すると、 こういったことが盲点となりがちですが、楽器ごと、人ごとにベストな弦高は違うと いうことも覚えておくようにしましょう。 |
(C) Copyright 2002. Ishibashi Music Co.,Ltd. All rights reserved.